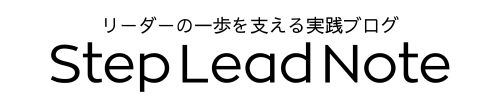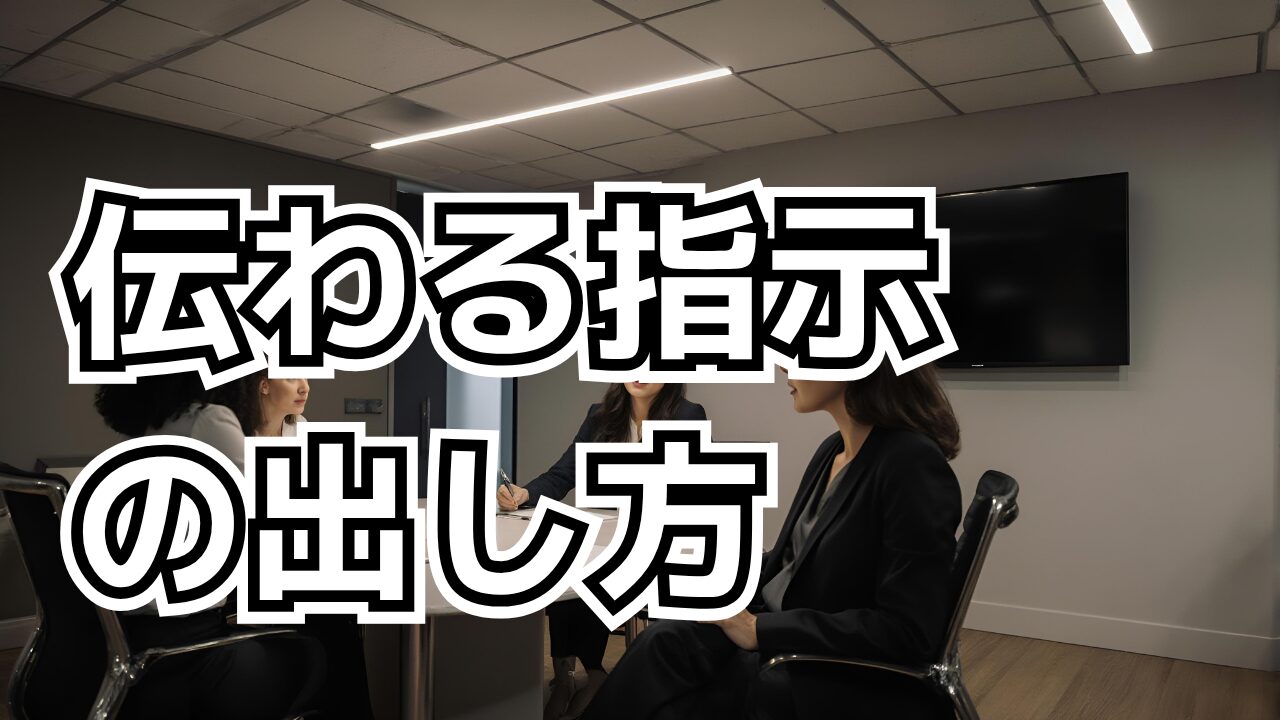- 「丁寧に指示したはずなのに、部下の認識がズレている…」
- 「結局、何が言いたいんですか?」と、部下を混乱させてしまった…
- 良かれと思って任せたのに、期待と違う成果物が上がってきて、結局自分がやり直す羽目になった…
- 指示待ちの部下が多く、チーム全体の生産性が一向に上がらない…
リーダーやチームをまとめる立場になったあなたが、もしこのような「伝わらない」という深刻な壁にぶつかっているなら、それは決してあなたの熱意や能力が低いからではありません。
原因は、リーダーとしての「伝わる指示の出し方」という、具体的で再現性のある技術を知らないだけなのです。
私自身もリーダーになったばかりの頃、「自分の頭の中では完璧に整理されているのになぜ伝わらないんだ」と、何度も歯がゆい思いをしました。
しかし、それは「伝え方」が「アート(感覚)」ではなく「サイエンス(技術)」であると理解することで、劇的に改善できたのです。
この記事では、多くのリーダーが無意識にやってしまっている「伝わらない指示」の根本原因を、具体的なNG例文と共に深く分析します。
その上で、誰でも今日から実践できる「部下が自ら動きたくなる指示出しの技術」を、具体的な7つのステップに分けて徹底的に解説します。
この記事を最後まで読めば、あなたは「指示待ち部下」を「自走できる部下」に変え、チームの無駄な手戻りをなくし、成果を最大化できます。
そして何より、あなた自身のリーダーとしての時間と心に余裕が生まれ、より本質的な仕事に集中できるようになるでしょう。
なぜあなたの指示は部下に響かないのか?「伝わらないリーダー」3つの根深い共通点
まず、多くのリーダーが陥りがちな「伝わらない指示」の典型例を見てみましょう。
この指示を受けた部下が、どんな気持ちで何に困るかを想像しながら読んでみてください。
【NG例文】 「A社の件、先方からいくつか質問が来ていて、例の資料の数字についてなんだけど、あれって確か先週の会議で共有された最新版のデータに基づいていたと思うんだけど、ちょっと確証が持てなくて。もし違っていたらクライアントに迷惑がかかるし、信頼問題にもなるから、念のためもう一度、関連部署にも確認した上で、今日中にA社へ提出する資料を修正しておいてくれるかな。よろしく。」
丁寧な言葉遣いですが、これでは優秀な部下ほど動き出せません。
なぜなら、この短い文章の中に、部下の思考を停止させてしまう「伝わらない」典型的な3つの原因が、すべて凝縮されているからです。
原因1:結論が最後(または、ない)〜相手の脳に負荷をかける話し方〜
背景や自分の懸念から話し始めるのは、聞き手の思考を暗いトンネルに誘い込むようなものです。「で、結局私に何をしてほしいの?」と、聞き手は結論という出口を探しながら話を聞く羽目になり、脳に多大な負荷がかかります。
【なぜこうなる?】
これは、「いきなり指示をすると高圧的だと思われるのではないか」「丁寧な印象を与えたい」という、リーダー側の無意識の配慮や不安が原因であることが多いです。しかし、その配慮が、結果的に相手の時間を奪い、混乱させるという本末転倒な事態を招いているのです。
原因2:一文が長く情報が渋滞している〜読解力が試される話し方〜
読点(、)を多用し、「〜で、〜して、〜だけど」と文章を無限に繋げていくスタイルです。
一つの文に「状況説明」「懸念」「依頼」「理由」など、複数の情報が詰め込まれることで、情報の交通渋滞が起きます。
【なぜこうなる?】
これは、リーダー自身が頭の中で考えながら話していることの現れです。
思考のプロセスをそのまま言葉にしているため、聞き手はリーダーの思考の迷路に付き合わされ、どこが重要な情報なのかを必死で取捨選択しなくてはなりません。
原因3:表現が曖昧で責任を丸投げしている〜部下を不安にさせる話し方〜
「〜と思う」「ちょっと」「いい感じに」「なるべく早く」といった曖昧な表現。
これらは一見、部下の主体性を尊重しているように聞こえますが、実際には判断基準と責任を部下に丸投げしています。
【なぜこうなる?】
「マイクロマネジメントだと思われたくない」「自分で考えてほしい」という思いからくるものですが、これは「放任」であり「育成」ではありません。
明確なゴールや制約条件を示さないまま自由を与えるのは、コンパスを持たずに航海に出すようなものです。
部下は「どこまでやればいいのか?」「失敗したらどうしよう?」と不安になり、結果的に行動が遅くなったり、当たり障りのない成果物しか出せなくなったりします。
【例文で徹底比較】部下が動く!劇的に伝わる「指示出し」7つの技術
では、先ほどのNG例文を、部下が迷いなく、かつ意欲的に行動できる「伝わる指示」に変えてみましょう。
ここには、成果を出すリーダーが必ず実践している7つの重要な技術が盛り込まれています。
【OK例文】 【要件】A社向け資料の修正依頼
1.【結論】 A社へ提出する資料を、本日17時までに修正してください。
2.【理由】 資料内のデータが最新版か再確認が必要なためです。現状では誤った情報を提供するリスクがあります。
3.【具体的作業①】 営業企画部の田中さんに連絡し、「10月第2週版の最新販売データ」を入手してください。
4.【具体的作業②】 そのデータに基づき、資料P.5のグラフと数値を更新してください。
5.【目的・背景】 この資料は、来週の重要な商談でA社の役員に提示するものです。
この商談の成功が、今期の目標達成の鍵を握っています。6.【期待する状態】 誰が見ても一目で「最新の正しいデータだ」と分かり、我々の提案の信頼性を高められる状態にしてください。
7.【フォロー体制】 まずは自分で進めてみてください。
もし15時の時点でデータの入手に手こずるなど、困ったことがあれば、すぐに私(すなお)に声をかけてください。
一緒に解決策を考えましょう。
いかがでしょうか。
この指示には、部下が迷う要素が一切ありません。
それだけでなく、「この仕事は重要だ」と認識し、意欲的に取り組めるよう工夫されています。
この文章を構成する7つの技術を、一つずつ詳しく解説します。
- 技術1:結論ファースト(PREP法)
まず「何をしてほしいか(結論)」を最初に伝える。これはビジネスコミュニケーションの鉄則「PREP法(Point→Reason→Example→Point)」の根幹です。最初にゴールを示すことで、部下は話の全体像を把握でき、安心して詳細を聞く態勢に入れます。 - 技術2:理由を添える
「なぜ」この作業が必要かを伝えることで、部下は作業の重要性を理解し、納得感を持って取り組めます。単なる「作業者」ではなく、「プロジェクトの一員」としての当事者意識が生まれます。「やらされ仕事」から「自分の仕事」へと意識が変わる、極めて重要なステップです。 - 技術3&4:行動を分解し、具体化する
「修正」という抽象的な言葉を、「①データを入手する」「②数値を更新する」という具体的なタスクに分解します。リーダーの頭の中では当たり前の手順でも、部下にとってはそうでないかもしれません。行動の解像度を上げることで、部下は迷わず最初の一歩を踏み出せます。 - 技術5:目的・背景を共有する
「理由」が“Why”なら、「目的」は“So What?”(だから何なのか)です。この作業が、チームや会社のより大きな目標(今回は「重要な商談の成功」)にどう繋がっているのかを示すことで、部下のモチベーションは飛躍的に高まります。「この仕事には価値がある」と感じてもらうための、リーダーの腕の見せ所です。 - 技術6:期待するゴール(状態)を示す 「何をすれば終わりか」という**完了の定義(Definition of Done)**を明確にします。「修正すること」がゴールではなく、「誰が見ても最新の正しいデータだと分かる状態」がゴールであると伝えることで、成果物のクオリティのズレをなくします。
- 技術7:フォロー体制を明示する 「丸投げ」ではなく「任せる」ための重要な要素です。「困ったら相談していい」という心理的安全性を担保することで、部下は安心して挑戦できます。「一人で抱え込まず、チームで解決する」という姿勢を示すことで、ミスを未然に防ぎ、部下の成長も促せるのです。
もう「伝わらない」で悩まない!明日からできる具体的な3ステップ
これらの技術は、意識と訓練によって誰でも身につけることができます。
日々の業務の中で実践できる、具体的なトレーニング方法を3ステップでご紹介します。
ステップ1:15秒で「結論」を言語化するトレーニング
誰かに話しかける前、チャットを打つ前に、一度立ち止まり、「相手に最もしてほしい行動は何か?」を一言で、15秒以内に言語化する癖をつけましょう。
「資料を修正してほしい」「会議の日程を決めてほしい」「この件について意見がほしい」など、この結論から話し始めることを徹底してください。
これだけで、あなたのコミュニケーションの8割は改善されます。
ステップ2:「読点(、)」を「句点(。)」に変える文章デトックス
自分の書いたメールやチャットを送信前に見直してみてください。
もし一文が3行以上にわたっているなら、それは情報過多のサインです。
「〜で、」「〜ですが、」で繋げている読点を、意識的に全て句点「。」に置き換えてみる練習をしましょう。
最初は文章がぶつ切りに感じるかもしれませんが、それで正解です。
まずは情報を正確に区切る技術を身につけることが、分かりやすさへの最短ルートです。
声に出して読んでみて、息が苦しくなったら長すぎるサインです。
ステップ3:「5W1Hチェックリスト」で指示の漏れを防ぐ
指示を出す前に、以下の項目が明確になっているか、頭の中でセルフチェックする習慣をつけましょう。
慣れるまではメモに書き出すのも有効です。
- Why(なぜ): この仕事の背景・目的は何か?
- What(何を): 具体的な作業内容とゴールは何か?
- Who(誰が): 担当者は明確か?
- When(いつまでに): 期限は具体的か?(例:「金曜中」ではなく「金曜15時」)
- Where(どこで): どこに提出・報告するか?(チャット、共有フォルダなど)
- How(どのように): 進め方のルールや参考資料はあるか?
このチェックリストが、あなたと部下の間の「言ったはず」「聞いていない」という悲劇的なすれ違いを防ぐ、強力なツールになります。
まとめ:「伝え方」はリーダーシップそのものである
リーダーの仕事とは、チームの能力を最大限に引き出し、一人では成し遂げられない成果を出すことです。
そのために最も重要なスキルが、今回ご紹介した「伝え方の技術」です。
これは単なるコミュニケーションテクニックではありません。
- 相手の時間を尊重し、
- 部下の思考の迷いをなくし、
- 安心して業務に集中できる環境を整える
という、リーダーシップそのものなのです。
私自身、多くの失敗からこの技術の重要性を痛感してきました。
しかし、リーダーが意識して伝え方を変えれば、チームは必ずそれに応えてくれます。
部下のパフォーマンスが上がり、チームの成果が向上し、何よりリーダーであるあなた自身の仕事が、驚くほどスムーズに進むようになるのです。
まずは明日、部下にかける一言から試してみてください。
あなたの言葉が変われば、部下の動きが変わり、チームが変わり、そしてあなた自身の評価も劇的に変わっていくはずです。